聴講日:2025年11月15日
千葉市にある敬愛大学で開催された
「房総戦国時代の終焉と秀吉・家康-千葉氏・里見氏・房総諸氏の運命は-」
を聴講してきました。
定員350人のところ、500人ぐらいの応募があったそうで、幸運にも当選となり、聴講することができました。
講演会は
第Ⅰ部
講演①「小田原合戦と房総」 黒田 基樹氏(駿河台大学教授)
講演②「豊臣政権と房総」 柴 裕之氏(東洋大学・駒沢大学非常勤講師)
第Ⅱ部
座談会「NHK 大河ドラマを語ろう」
となっており、一番印象に残った芝先生の講演内容に対する感想を書きたいと思います。
豊臣政権と房総
小田原合戦前、里見氏は安房国と上総国の一部を支配していたが、上総国における里見領は没収された。
→
里見氏は小田原北条氏と同盟を結んでいましたが、それを破棄し、豊臣方に味方しました。運が良ければ、領土はすべて安堵になったかもしれませんが、豊臣政権の徳川家をとおした東国支配の確立のためには上総国の所領の没収は致し方なかったと思います。また徳川家が天下を取るという後の歴史を知っていると、安房国の代わりに北関東や東北のどこかに移封のほうが良かったと思えます。
関東に移封となった徳川家は上総国に鳥居元忠、下総国に本多忠勝を配置した。下総国は常陸国の佐竹氏や東北に備える場所であり、鳥居元忠は関東移封前から徳川領国の東の端を守る存在であった。
→
鳥居元忠が「徳川領国の東端を守る存在」ということは知らなかったので、印象に残りました。Wikipediaの鳥居元忠を見ると
戦後家康より甲斐国都留郡(山梨県都留市)を与えられ、初め岩殿城に入り、やがて谷村城主となる。この地域は武田氏統治時代においても小山田氏が独自の支配体制を確立していた上、北条氏との国境地域であった
と書かれており、確かに徳川領の東端を任されています。
また後の歴史を知っていると佐竹氏をついつい親豊臣と認識してしまい、鳥居元忠を配置し、厳重に警戒する必要もなかったのではと思ってしまいますが、徳川家の移封当時はまだ佐竹氏が信用できなかったので、鳥居元忠を配置したのは納得できます。
上総国の統治領域を没収された里見氏への備えとして、上総国への配置は重要であり、秀吉の承諾が求められた。
→
徳川家の有力武将の配置は家康ではなく、秀吉が決めたという話を聞いたことがありましたが、家康が決め、それを秀吉が追認したという形が正解なのでしょうか。
徳川と里見を比較すると、徳川のほうが圧倒的に大きく、本多忠勝を配置するほどでもないと思ってしまいますが、小田原合戦後の混乱で何があってもおかしくないので、万が一に備え信頼のできる本多忠勝を配置したと思います。
また俗説として秀吉は戦後間もない関東に徳川家を配置し統治に失敗したら取り潰そうと考えていたと言われることもありますが、秀吉の承認の下、本多忠勝が上総に配置されたのならば、そのようなことは無かったと分かります。
最後に
講演会は大学の教室で開催され、何十年ぶりに大学の教室に入ったので、何か懐かしい気がしました。敬愛大学では来年も講演会を予定しているそうで、興味のあるテーマならば、聴講したいと思います。

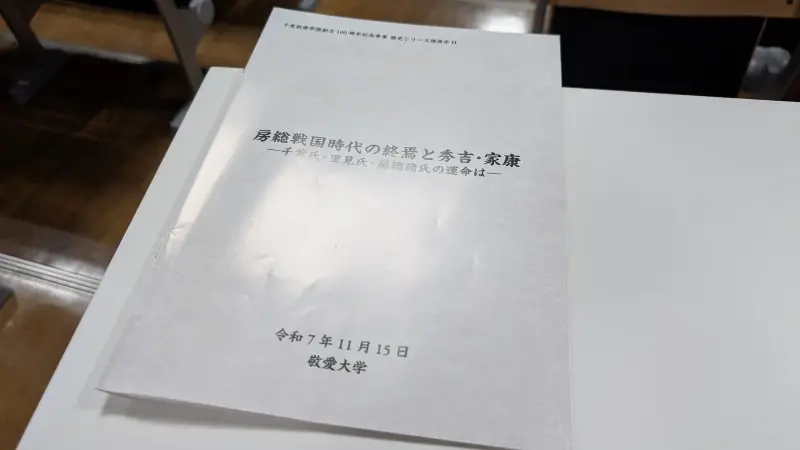
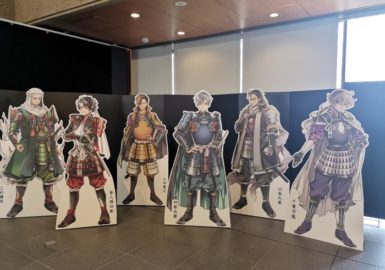




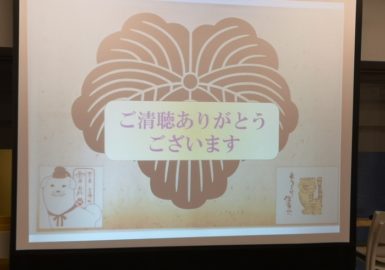

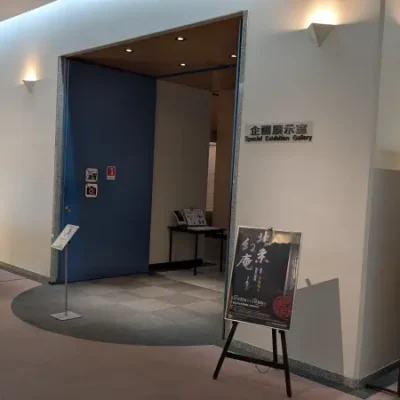
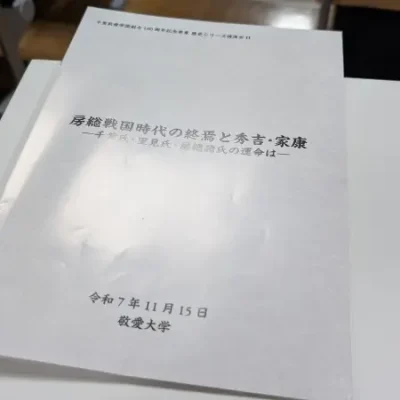


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/19cfef2a.4af5a5c2.19cfef2b.f264f2d1/?me_id=1213310&item_id=20533148&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9881%2F9784562059881_1_2.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
この記事へのコメントはありません。