訪問日:2022年3月13日
本サイトは彦根城の世界遺産登録を応援していますので、滋賀県が主催する彦根城関係のツアーがあれば、出来るだけ参加したいと思っています。そんな中、
「近江の城」魅力発信事業・連続講座「近江の城郭~豊臣の城・徳川の城」第3回「今に残る城と町・彦根城」
が開催されると知りましたので、早速申し込みをし、参加できることになりました。
当日は集合場所の彦根駅に向かい、受付後、時間通りにツアーは始まり、見学前に少し話がありました。そこでは、
・今回の講座は外堀の跡を歩き、その後、城内(内堀内)に入る。彦根城は特別史跡であるが、内堀の中だけを見て帰る人がほとんどで、外堀も史跡としては重要であるので、今回はそこを注目してほしい。
という旨が印象に残りました。
切通口、油懸口、高宮口、池州口
彦根駅から駅前お城通りを歩き、護国神社前へ。ここで見られる空堀が現存する唯一の外堀とのことです。彦根城を訪れたことがある方ならば、必ず目にしたことがあると思いますが、唯一の現存外堀ということは言われないと気付かないことでしょう。

彦根城 外堀跡
彦根城の外堀には7つの入口があり、今回はその中、4つの入口(切通口、油懸口、高宮口、池州口)を訪れます。まずは切通口です。切通口は現在の彦根キャッスルリゾートの駅から見て左側にあり、「切通口御門跡」と書かれた小さな石碑があります。当日頂いた資料に切通口御門模式図が掲載されており、イメージが掴めました。
次は油懸口です。油懸口は現在の彦根商工会議所やNTT西日本滋賀支店彦根別館の近くにありました。その辺りで中濠東西通りは斜めに曲がっていますが、旧道は直角に曲がっていたそうです。三角形の小さな「ヘタ地」がそのことを教えてくれています。
次は高宮口です。油懸口から高宮口までの間は見どころが多いです。蓮華寺の側を通る細い道は土塁を上り下りしていると分かる道でした。少し歩くと外馬場公園に到着。外馬場公園と隣の駐車場の敷地の大半は外堀だったそうです。確かに言われれば、そんな気がします。外馬場公園の隣に金亀会館があります。藩校弘道館の講堂を移築した建物であり、現在は内部を見学できないですが、見学できるようになれば、彦根観光の一つの見所になると思います。

外馬場公園と駐車場
金亀会館から少し歩くと外堀の隅部に到着。こちらには外堀土塁跡がはっきりと残り、また側の道もクランク状になっており、良い感じです。そこからしばらく歩くと高宮口に到着です。こちらには「高宮口御門跡」と書かれた小さな石碑がありました。

外堀土塁跡
次は池州口(本町口)です。高宮口から池州口までは大津能登川長浜線を歩きましたが、こちらの道は外堀跡であり、道路の側面が右に向かって下がっているのがその証とのことです。道路を本町2丁目交差点で右折すると、江国寺の立派な山門が目に入りました。この辺りが池州口御門跡です。

江国寺 山門
彦根城の外堀には7つの入口がありましたが、今回のツアーは4つの入口で終了となり、この後はお城の中心に向かいます。
宗安寺、京橋口
池州口跡から夢京橋キャッスルロードに出て、少し歩くと宗安寺に到着。宗安寺には以前訪れたことがあり、改めて、本ブログで訪問記を書きたいお寺です。彦根城は築城当初は対大坂(豊臣)ということもあり、池州口が最重要の入口だったと思いますので、その近くにある宗安寺も重要なお寺だったと思います。
夢京橋キャッスルロードに戻り、しばらく歩くと、中堀の京橋口に到着。彦根城は中堀に面して4つの門があり、京橋口はその一つです。枡形になっており、ガイドの方が話されていましたが、向かってくる車が直前まで見えないので、現代でも枡形の怖さを感じられます。
登り石垣
京橋口からしばらく歩き、大手口御門へ到着。こちらには登り石垣があります。登り石垣は彦根城を代表するものの一つだと思います。ちなみに彦根城には登り石垣が全部で5つあります。

大手門近くの登り石垣
登り石垣は竪堀とセットであり、ガイドの方は竪土塁と竪堀の進化形と考えるそうです。登り石垣は倭城にもあるので、大陸の技術を持ち込んだ説もあるそうです。また彦根城には、枡形虎口、竪堀などお城の防御の全てを見ることができるので、「究極の戦国の城」、「お城の教科書」とも言えるとのことです。
登り石垣は石垣ばかりに目が行き、竪堀には注意が向いていませんでした。今回、改めて見ると、登り石垣と隣接して竪堀があるのを確認できました。
東の大堀切、鐘の丸、着見台、西の丸、西の大堀切、井戸曲輪
尾根を断ち切るのは土の城ではよくありますが、石の城でそれをやっているのが彦根城の大堀切とのことです。また現在は橋の橋脚は地面に付いていますが、元々は石垣に付いていたそうです。

天秤櫓と橋
鐘の丸は彦根城築城時に一番最初に整備された曲輪であり、大手門を守る場所とのことです。着見台は参勤交代時に使われる方向を監視する場所とのことです。確かに着見台から佐和口多聞櫓などがよく見えました。

着見台から見た佐和口多聞櫓など
西の丸、西の大堀切がある西側は東側に比べて、防御が手薄な感じがしますが、大堀切の先には登り石垣があり、西側の防御も十分に凄いと感じられます。

米蔵跡側の登り石垣(上から)

米蔵跡側の登り石垣(下から)

玄宮園側の登り石垣(上から)

玄宮園側の登り石垣(下から)
井戸曲輪には、石垣が帯状に広がっており、彦根城ではここだけで見られるそうです。石垣は非常に迫力があり、密かな映えスポットとして知られているそうです。

井戸曲輪近くの石垣
ツアー終了後
ツアー終了後、登り石垣の写真などを撮るため、内堀内を巡りました。
大手道は格好良いです。大手道を上っていると、今から殿様に会うという気分になり、第二期工事以前、重臣の屋敷は内堀内にあったので、本丸に住んでいた大名(井伊家)と米蔵跡辺りに住んでいた家臣の身分差を示すために大手道があったという説に納得がいきます。

大手道
太鼓門櫓に人が入っているのが見えたので、私も入りました(実は太鼓門櫓の中に入れるとは今まで知りませんでした)。

太鼓門櫓からの景色
最後に
外堀の入口跡を見てから、京橋口、大手口を通って、内堀内を見学したことにより、「外堀を含めたものが彦根城である」と認識でき、非常に有意義でした。



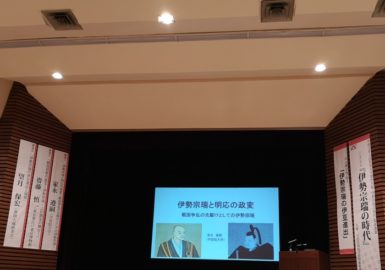

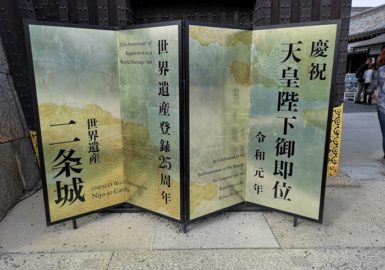




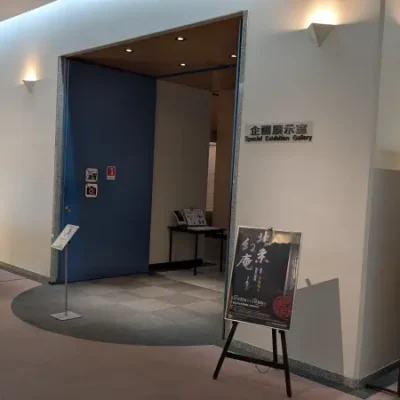
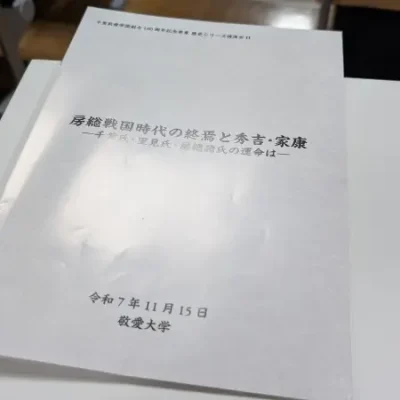


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/19cfef2a.4af5a5c2.19cfef2b.f264f2d1/?me_id=1213310&item_id=20381151&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4495%2F9784120054495_1_3.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
この記事へのコメントはありません。