訪問日:2019年6月22日
東京国立博物館では毎月、月例講演会を開催しており、6月のタイトルは「日本のよろい」でした。東京国立博物館のサイトには
日本のよろい(甲冑)は、武具であると同時に、様々な材料や技術が集められた美術工芸品です。その見どころと魅力をわかりやすくご紹介します。
とあり、私はよろい(甲冑)に関しては全然知識がないので、甲冑に関する知識を増やす良い機会だと思い、聴講することにしました。
日本のよろい
よろいはサムライアート
・甲冑は刀剣と並ぶ武士のシンボル
・戦場での活躍をアピールする → 力強さ、美しさが求められる
・多様な色彩と造形 → 武士の美意識が表現される
日本のよろいの種類
(1) 大鎧
・平安時代後期に登場
・騎馬武者が着た大型で重いよろい
・室町時代以降、実践ではほとんど使用されなくなる
・草摺(くさずり)が4枚
(2) 胴丸
・平安時代後期に登場
・徒歩で戦う武士用のよろい
・胴の合わせ目が右側にある
・草摺が8枚
(3) 腹巻
・鎌倉時代に登場
・徒歩で戦う武士用のよろい
・胴の合わせ目が背中にある
・草摺が7枚
(4) 当世具足
・安土桃山時代に登場
・各種防具で全体を隙間なく守る
・背中に旗を立てる部品がある
・変わり兜が備わる場合がある(変わり兜:上級武士が合戦で自らの活躍をアピールするため、個性的で人目を引く奇抜なデザインの兜)
日本の甲冑には上記4種類があり、戦い方の変化(騎馬戦から徒歩集団戦)、武器の進化(弓矢から鉄砲)により、よろいの主流が変化した。
日本のよろいの材料と技術
・小札(こざね)
日本のよろいを形づくる最も基本的なパーツ。鉄製と牛革製があり、鉄は丈夫さ、革は軽さという特徴があり、鉄製と革製小札を交ぜて、丈夫さと軽さを両立した。小札をつないで札板(さねいた)とする。
・威(おどし)
小札の穴に紐を通し、つなぎ合わせること。紐のことを威毛と呼ぶ。威により、防御力と可動性を両立。威毛を染色し、組み合わせにより、様々な色彩とデザインが生まれる。
岡山に伝わった奇跡のよろい 国宝 赤韋威鎧
・赤韋威鎧とは、赤色に染めた韋で全体を構成する小札の札板を威した大鎧のこと。
・現存する大鎧のほとんどは後世の破損や修復によって大きく改変されているが、(赤韋威鎧は)ほとんど改変を受けていない。
・神社への奉納品ではなく、実戦で使用した甲冑が赤木一族に相伝されたもので、由来伝来がはっきりしている。
講演終了後
東京国立博物館の本館2階に展示してある大鎧、胴丸、腹巻、当世具足を見ると、講演を聞く前より、はるかに色々なことが分かりました。まだまだ甲冑に関しては初心者ですが、本などを購入して、更に深く学びたいと思えた良い講演会でした。
赤韋威鎧が東京国立博物館で展示された時は必ず見に行きたいと思います。




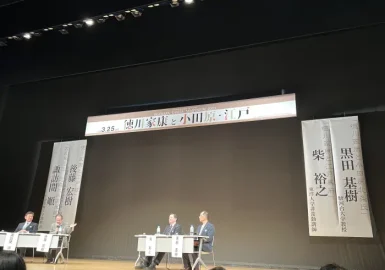








![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/19cfef2a.4af5a5c2.19cfef2b.f264f2d1/?me_id=1213310&item_id=20533148&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9881%2F9784562059881_1_2.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
この記事へのコメントはありません。